30 件 見つかりました。
2025年1月29日のヲハニュースをお届けします。

とはいえ、確かに窓あってもいいな。

ChatGPT超えの中国AI「DeepSeek-R1」の衝撃
低価格で参入「窓のない部屋」は本当につくれるか?ミステリあるあるを建築士が検証【建築知識連載試し読み】 | エクスナレッジ・オンライン|知識が深まる、世界が広がる
おもしろい!とはいえ、確かに窓あってもいいな。
空港でスーツケースを預けた後、”異常に重過ぎる”という理由で呼び出しがかかり複数人の空港職員に囲まれた状態で確認した様子がこちら→「これは密輸ですわ」
サッポロクラシック、ここ数年東京都心部のコンビニやスーパーでちょくちょく見かける。レア度は秋味とか冬物語くらいか【MOS】いつも脇役のオニ(鬼)オンフライが“節分の日”は主役に!「鬼盛りオニオンフライ」を節分に合わせて3日間限定販売
鬼オン!いいね!【独自解説】命令ナシで人を動かす⁉ノーベル賞受賞の“現代の魔法”『ナッジ理論』 言うことを聞かない夫、買い過ぎちゃう私、片付けない子ども…ダメな自分・家族を変えられるマル秘テクを第一人者が紹介!|YTV NEWS NNN
ライフハーーーーーック!「恋人がいる人を略奪する手法」が営業で取引先にアプローチする時にも有効という話→「彼氏持ちが合コンに来た時使ってる」
交際相手(既存取引先)を肯定する、と「運の悪さとは、本人の再現性の高い習慣から来てる」というツイートをみて習慣を変えて行動を改善したら、お見合いできる層がかわって成婚できた話
知らないおっさんに絡まれる、いきなり怒られる。なんで私はこんなに運が悪いんだ……繰り返される運の悪さにはこういうケースもあるかもね、という話
と言う人と一緒に行動してみたら、人通りの邪魔する行動ばかりして指摘しても本人が治さないだけだった。
生島ヒロシ、TBSラジオ緊急降板「人権方針に背く重大なコンプライアンス違反」 - 芸能 : 日刊スポーツ
ほう森永卓郎さん死去 67歳 がん闘病中も力尽き28日自宅で…長男康平氏「まだ気持ちの整理が」 - おくやみ : 日刊スポーツ
おくやみもうしあげますニューヨーク・タイムズが報じる「中居正広の性加害とフジのグダグダぶり」 | 「中年の元アイドル」の性スキャンダル
「見て見ぬふりをしてはいけないという認識が広まるのに時間がかかりました」と前出の本間は言う。
「大口の顧客が離れて初めて、行動が起こされるのです」
読書感想記事リスト(2017年7月・8月・9月)
2017-09-30-2
[MonthlyBook]
2017年7月〜9月に書いた読書感想記事のリストです。
全部で66タイトル(電子書籍1, 紙書籍65, オーディオブック0)でした。
ゾロリ61冊をカウントしてるので読書家だと思われる!!
■松村真宏 / 仕掛学 - 人を動かすアイデアのつくり方 [Kindle版]
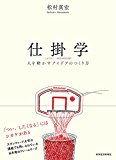
■原ゆたか / かいけつゾロリのかいていたんけん(かいけつゾロリシリーズ61)
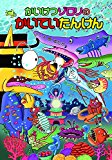
■原ゆたか / かいけつゾロリシリーズ 30周年スペシャルAセット(全30巻)
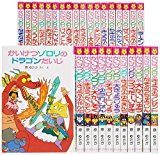
1〜30巻
■原ゆたか / かいけつゾロリシリーズ 30周年スペシャルBセット(既刊30巻)
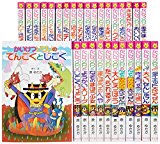
31〜60巻
(ref. [2017-07-13-1])
■やましたひでこ / 新・片づけ術「断捨離」

■奥野宣之 / 人生は1冊のノートにまとめなさい - 体験を自分化する「100円ノート」ライフログ

■びじゅチューン! DVD BOOK 3

■佐藤 理史 / コンピュータが小説を書く日 --AI作家に「賞」は取れるか

全部で66タイトル(電子書籍1, 紙書籍65, オーディオブック0)でした。
ゾロリ61冊をカウントしてるので読書家だと思われる!!
電子書籍
■松村真宏 / 仕掛学 - 人を動かすアイデアのつくり方 [Kindle版]
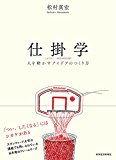
「ついしたくなる」にはシカケがある。(ref. [2017-09-22-1])
スタンフォード大学の講義でも用いられている、日本発のフレームワーク、仕掛学【Shikakeology】。
押してダメなら引いてみな。一言で言うとこれが仕掛けの極意です。
人に動いてほしいときは無理やり動かそうとするのではなく、自ら進んで動きたくなるような仕掛けをつくればよいのです。
ただ、言う は易し行うは難し。そのような仕掛けのつくり方はこれまで誰も考えてきませんでした。
本書では仕掛けの事例を分析し、体系化。
「ついしたくなる」仕掛けのアイデアのつくり方についてご紹介します。
紙書籍
■原ゆたか / かいけつゾロリのかいていたんけん(かいけつゾロリシリーズ61)
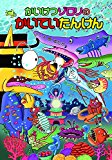
いたずらの王者をめざすゾロリとイシシ・ノシシは、たまて箱とかわいい乙姫さまにあうため海のそこへたんけんにしゅっぱつ! りゅうぐうじょうを目指します。でも、深い海のそこには、ダイオウイカやシンカイザメなどへんてこなが生き物ばかり……。ゾロリたちはぶじに帰ってこられるのでしょうか?(ref. [2017-07-06-2])
■原ゆたか / かいけつゾロリシリーズ 30周年スペシャルAセット(全30巻)
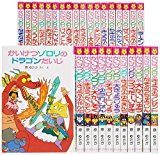
1〜30巻
■原ゆたか / かいけつゾロリシリーズ 30周年スペシャルBセット(既刊30巻)
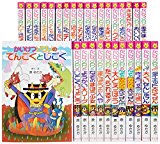
31〜60巻
(ref. [2017-07-13-1])
■やましたひでこ / 新・片づけ術「断捨離」

ヨガの行法哲学をもとにクラター・コンサルタントのやましたひでこさんが提唱する「断捨離」。家のガラクタを片づけることで、心のガラクタも整理して、人生をごきげんへと入れ替える「新・片づけ術断捨離」はクチコミで一気にブームに。全国に“ダンシャリアン”(「断捨離」を実践する人)が急増中です。(ref. [2017-07-19-1])
■奥野宣之 / 人生は1冊のノートにまとめなさい - 体験を自分化する「100円ノート」ライフログ

デジタルでは残せない世界でただ一つの体験記の作り方。100円ノート整理術第3弾。(ref. [2017-07-28-1])
■びじゅチューン! DVD BOOK 3

「びじゅチューン! 」(NHK Eテレ)は、世界の有名な美術作品をモチーフにしたユニークなうた&アニメーション。(ref. [2017-08-15-2])
アーティストの井上涼が、作詞、作曲、歌唱、アニメーション制作のすべてをてがけています。
■佐藤 理史 / コンピュータが小説を書く日 --AI作家に「賞」は取れるか

2016年3月21日、東京都内での「星新一賞への応募報告会」。コンピュータを利用して作成した作品の応募が11件、そのうち代表者が報告会に出席した2つのプロジェクトからそれぞれ2編あり、少なくとも1編が一次選考を通過したと主催者側から報告された。「囲碁の次は小説?」「作家もうかうかしていられない」マスコミが速報し、反響は広く海外にまで及んだ。人工知能が小説を「書いた」?-今回のプロジェクトを発端からクールに精緻に振り返り、日本語で文章を紡ぐことの複雑さを痛感し、AIと創作の関係にまで思いをはせた貴重なメイキングの記録。(ref. [2017-08-29-2])
2017年9月27日のヲハニュースをお届けします。

みんな本当の理由を隠しているという印象。
そうでもないか。
以下、随時追加。
相関があると言ってるだけの話なので一部の例外を出しても否定材料にならない。
とはいえ、因果関係と相関関係の違いがわからない人が多いのでこういう話は誤解を招き危険。
炎上を狙う目的でないならば、ポリコレ的に避けるのが吉。
子供がディズニーランド行きたいって言ったら休んで行けば良いかと。
そんな仕掛けの話。

たつき/irodoriさんのツイート: "突然ですが、けものフレンズのアニメから外れる事になりました。ざっくりカドカワさん方面よりのお達しみたいです。すみません、僕もとても残念です"
ネット界隈で話題の「けものフレンズ」監督降板騒動。みんな本当の理由を隠しているという印象。
そうでもないか。
- たつき監督、「けものフレンズ」続編から降板か Twitterで明らかに - ITmedia NEWS
- 「けものフレンズ」たつき監督降板騒動、原因は制作会社との条件不一致 製作委員会が正式にコメント - ねとらぼ
- けもフレ、たつき監督が降板「カドカワ方面からのお達しみたい」 売れると主導権争い、の指摘が : J-CASTニュース
- <東証>カドカワが軟調 人気アニメの監督降板、悪影響を懸念 :日本経済新聞
- Amazon.co.jp: けものフレンズBD付オフィシャルガイドブック 全6巻セット: : Book

- Amazon.co.jp: けものフレンズ ラッキービーストBIGぬいぐるみ: Toy
以下、随時追加。
何これ → たーのしー! → 助けて → ありがとう → 返してよ! ニコニコ「けもフレ」1話公開日から激動を振り返る - ねとらぼ
- たつき監督けものフレンズ降板関連ニュースまとめ - まなめはうす
- たつき監督のけもの騒動、けものフレンズ正常化に向けて企業トップ級が協議へ : 市況かぶ全力2階建
林修先生、キラキラネームと学力の相関性語る 東大合格者の名前は… (デイリースポーツ) - Yahoo!ニュース
直接の因果関係はないが相関関係はある。相関があると言ってるだけの話なので一部の例外を出しても否定材料にならない。
とはいえ、因果関係と相関関係の違いがわからない人が多いのでこういう話は誤解を招き危険。
炎上を狙う目的でないならば、ポリコレ的に避けるのが吉。
小学生の息子が友だちを全員「さん」付けで呼ぶから
学年始まりにもらってきた名簿を暗記する勢いでよく見ている東京ディズニーランドに行くという理由で保育園の行事を休ませるか、激しく迷い中 - Bygones !
保育園って保護者が仕事休むときはあずけられないって決まりだったな。子供がディズニーランド行きたいって言ったら休んで行けば良いかと。
【読書感想文】仕掛学 - 人を動かすアイデアのつくり方
ついついやっちゃう動作が別のことに役に立つ!そんな仕掛けの話。
9月22日スタートのKindleセール「最大50%還元 講談社1万冊」「新本格ミステリ」「2000年代連載開始マンガ」「新書フェア」「戦記もの」「哲学入門書」など (2017.9.23)
金曜スタートの分。スマホからPCに「フリック入力」可能 大学生エンジニアが1時間でサービス開発 - ITmedia NEWS
WebRTCLDRが終了することについて - ogijun's blog
ニャンコリーダー期待。小型犬がサッカー公式戦に乱入!華麗なドリブルを披露し、試合後なぜかインタビュー アルゼンチン1部: カルチョまとめブログ
これはわんかわいい
2017年9月22日のヲハニュースをお届けします。

▼ネットの「炎上」 関与は3%と少数 文化庁が調査 | NHKニュース
なお、1年半前の調査記事でもごく少数とのこと。
実際すごく少ないんでしょうね。
▼「恋ダンス」動画消す苦悩 拡散させたい、でも売れない:朝日新聞デジタル
レコード会社が時代遅れなだけか。
youtube動画広告収入を自社が得るようにすれば良かったのに。
仕組みあるんだから。
▼『ブログビレッジ~ブログを教えないブログサロン~』に1ヵ月入会して結果、500円でも高すぎだった。 - ユトピの60%ぶろぐ
ああ
▼日本人主導のビットコイン・バブルは崩壊へのカウントダウンに入った : 金融日記
ほぼすべて売ってしまってから書いてるのかなあ
▼周りに理解してもらいにくい離婚の理由 - ココッチィ
コミニュケーションとらないんなら仕方がない。
とれないんだから。
▼売り場でおっぱい丸出し!? ところ変われば授乳も変わる!スペイン育児見聞録 by ハラユキ - 赤すぐ 妊娠・出産・育児 みんなの体験記
あっけらかんとしているね。
▼ご注意:32ビットアプリはiOS11で動かなくなる——アップデートすると多くのゲームが忘却の彼方へ - TechCrunch Japan
困るアプリがいくつかある。
なくなるとこまるー!
▼スマホからPCに「フリック入力」可能 大学生エンジニアが1時間でサービス開発 - ITmedia NEWS
WebRTC
▼【読書感想文】仕掛学 - 人を動かすアイデアのつくり方
ついついやっちゃう動作が別のことに役に立つ!
そんな仕掛けの話。

▼ネットの「炎上」 関与は3%と少数 文化庁が調査 | NHKニュース
文化庁がことし、全国の16歳以上の男女、およそ3500人を対象に実施し6割から回答を得ました。
インターネット上にある意見を書き込んだ場合、批判的な意見が殺到する、いわゆる「炎上」を目撃した場合、書き込みや拡散をするか聞きました。
「ほとんどしないと思う」と答えた人は10.1%、「全くしないと思う」は53.2%で、全体の6割を超えました。一方で、「大体すると思う」、「たまにすると思う」と答えた人は、合わせて2.8%とごく一部であることがわかりました。調査結果。
なお、1年半前の調査記事でもごく少数とのこと。
実際すごく少ないんでしょうね。
▼「恋ダンス」動画消す苦悩 拡散させたい、でも売れない:朝日新聞デジタル
レコード会社が時代遅れなだけか。
youtube動画広告収入を自社が得るようにすれば良かったのに。
仕組みあるんだから。
▼『ブログビレッジ~ブログを教えないブログサロン~』に1ヵ月入会して結果、500円でも高すぎだった。 - ユトピの60%ぶろぐ
ああ
▼日本人主導のビットコイン・バブルは崩壊へのカウントダウンに入った : 金融日記
ほぼすべて売ってしまってから書いてるのかなあ
▼周りに理解してもらいにくい離婚の理由 - ココッチィ
コミニュケーションとらないんなら仕方がない。
とれないんだから。
▼売り場でおっぱい丸出し!? ところ変われば授乳も変わる!スペイン育児見聞録 by ハラユキ - 赤すぐ 妊娠・出産・育児 みんなの体験記
あっけらかんとしているね。
▼ご注意:32ビットアプリはiOS11で動かなくなる——アップデートすると多くのゲームが忘却の彼方へ - TechCrunch Japan
困るアプリがいくつかある。
なくなるとこまるー!
▼スマホからPCに「フリック入力」可能 大学生エンジニアが1時間でサービス開発 - ITmedia NEWS
WebRTC
▼【読書感想文】仕掛学 - 人を動かすアイデアのつくり方
ついついやっちゃう動作が別のことに役に立つ!
そんな仕掛けの話。
【読書感想文】仕掛学 - 人を動かすアイデアのつくり方
2017-09-22-1
[BookReview][Kindle]
仕掛学の「仕掛け」って、デザイン思考とかと同じで、基本的には「とんち」による問題解決。
しかし確固としたポリシーによる定義がある。
定義があるから「学」になるんですよね。
「なるほど」な事例がたくさんでおもしろいです。
■松村真宏 / 仕掛学 - 人を動かすアイデアのつくり方 [Kindle版]
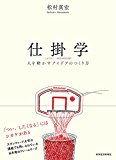
「仕掛け」とは「行動を変えるきっかけになるもの」。
心のエンジンのスタートボタンを押すようなものですね。
きっかけそのものではなく「結果として」達成されるというのが重要。
ゴミ箱の上にバスケットボールがあるからゴミを投げ入れたくなって結果として整理整頓となる、という感じ。
うまい仕掛け=トンチによる解決、ですよね、やっぱり。
なお、「仕掛け」のちゃんとした定義については本書でしっかり述べられているのでそちらをどうぞ。
目次:
しかし確固としたポリシーによる定義がある。
定義があるから「学」になるんですよね。
「なるほど」な事例がたくさんでおもしろいです。
■松村真宏 / 仕掛学 - 人を動かすアイデアのつくり方 [Kindle版]
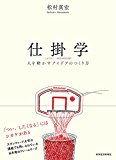
「ついしたくなる」にはシカケがある。
スタンフォード大学の講義でも用いられている、日本発のフレームワーク、仕掛学【Shikakeology】。
押してダメなら引いてみな。一言で言うとこれが仕掛けの極意です。
人に動いてほしいときは無理やり動かそうとするのではなく、自ら進んで動きたくなるような仕掛けをつくればよいのです。
ただ、言う は易し行うは難し。そのような仕掛けのつくり方はこれまで誰も考えてきませんでした。
本書では仕掛けの事例を分析し、体系化。
「ついしたくなる」仕掛けのアイデアのつくり方についてご紹介します。
「仕掛け」とは「行動を変えるきっかけになるもの」。
心のエンジンのスタートボタンを押すようなものですね。
身近な整理整頓一つとっても、線を引いたり、バスケットゴールを設置したり、ぬいぐるみを使ったり、足跡を使うなどさまざまなアプローチがある。
このような行動を変えるきっかけになるものを本書では「仕掛け」と呼んでいる。
無理やり行動を変えさせようとするのではなく、つい行動を変えたくなるように仕向けるのである。
きっかけそのものではなく「結果として」達成されるというのが重要。
ゴミ箱の上にバスケットボールがあるからゴミを投げ入れたくなって結果として整理整頓となる、という感じ。
もともと何もなかったところに新たな行動の選択肢を追加しているだけなので、最初の期待から下がることはない。どの行動を選んでも自ら選んだ行動なので、騙されたと思って不快に思うこともない。つまり、仕掛けは誰の期待を下げることもなく問題を解決することができる方法になる。
仕掛けは装置によって問題解決をはかるのではなく、人々の行動を変えることで問題解決をはかる。この発想の転換が仕掛けの肝であり、装置中心アプローチの視点を行動中心アプローチの視点に変えることで新しいアプローチが見えてくる。
うまい仕掛け=トンチによる解決、ですよね、やっぱり。
行動と解決する問題の関係が一見すると無関係に見えるときほどうまい仕掛けになる。このような仕掛けの性質を「仕掛けの副作用性★8」と呼んでいる。
なお、「仕掛け」のちゃんとした定義については本書でしっかり述べられているのでそちらをどうぞ。
目次:
- 世界は「仕掛け」にあふれている
- 序章 「ついしたくなる」には仕掛けがある
- 天王寺動物園の筒
- 行動で問題を解決する
- 思わず整理整頓したくなる方法
- 人の行動を変える奥義
- 狙いたくなる便器の的
- 良い仕掛けと悪い仕掛け
- 仕掛けを定義する3つの要件
- 仕掛けが活躍する場所
- 1章 仕掛けの基本
- 行動の選択肢を増やす
- 行動を上手に誘導する
- 結果的に問題を解決する
- 強い仕掛けと弱い仕掛け
- インパクトはいずれ薄れる
- 行動中心アプローチ
- 仕掛けもどきに注意
- 正論が効かないときの処方箋
- 2章 仕掛けの仕組み
- 仕掛けの原理
- 仕掛けの構成要素
- [大分類]物理的トリガ/心理的トリガ
- [中分類]フィードバック
- [小分類]聴覚/触覚/嗅覚/味覚/視覚
- [中分類]フィードフォワード
- [小分類]アナロジー/アフォーダンス
- [中分類]個人的文脈
- [小分類]挑戦/不協和/ネガティブな期待/ポジティブな期待/報酬/自己承認
- [中分類]社会的文脈
- [小分類]被視感/社会規範/社会的証明
- トリガの組み合わせ
- 3章 仕掛けの発想法
- 仕掛けを見つける方法
- 要素の列挙と組み合わせ
- 仕掛け事例を転用する
- 行動の類似性を利用する
- 仕掛けの原理を利用する
- オズボーンのチェックリスト
- 一方ロシアは鉛筆を使った
- 考案した仕掛けの例
- おわりに
- 参考文献
Powered by chalow