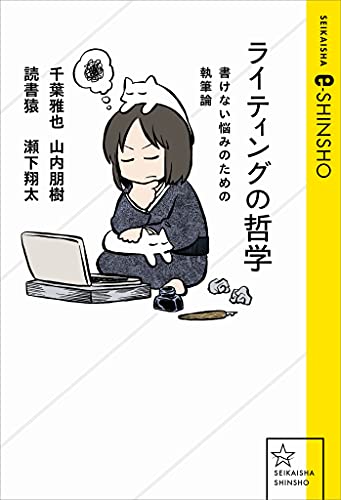
まず最初に著者の4人による座談会が開催されます。
執筆についていろいろ語り合います。
で、それを受けて各自が8000文字ほどの原稿を書きます。
4人の文章が提示されます。
で、最初の座談会から2年後にまた4人による座談会。
感想会、反省会みたいな感じで、執筆を振り返りながら語り合います。
そんな内容です。
四者四様で面白いです。
ただ、参考にはなるけど、結局一人一人が自分にあうツールや方法や哲学を走りながら見つけていかなきゃなあ、という思いが強くなりました。
私の今の執筆環境にダイレクトに活かせそうなことはそれほどありませんでしたが、それでもヒントはいっぱい得られたので、間接的に活かせることはたくさん。
以下、読書メモ的なもの。
もともとは、アウトライナーなどの情報交換の座談会から始まったみたいで、様々なツールが紹介されています。出てきたのをメモ: Acta, Tree, Inspiration, WorkFlowy, Evernote, OmniOutliner, OmniFocus, EG Book, PageMaker, QuarkXPress, Jedit, 紙copu, mi, Scrivener, MemoFlowy, Ulysses, stone, SnapWriter など。何かしらベースとなるエディタがあって、文章が最終的にそこへ至るまでにいろんなツールを経由していく感じですね。
庭の専門家、山内さん。庭づくりとの類似性について。
文章を書くという行為も、どうやって制約をつくりだし、配置するかが重要になってくると思う制限が大切(重要)な要素ということは他の方も言及。
時間の制約(〆切)の現実性による「諦め」でそぎおとされて仕上がる、みたいな話もしてました。
それは確かにそうなんだけど、あまり利用したくない制約ではあります。
千葉 [...]いま頭のなかで思っていることを全部、ジャンルもごちゃまぜでWorkFlowyにどんどん書いてしまうわけです。「えーっと」とか「今日はフリーライティングしてみるわけだけど」とかもひとつひとつ全部、箇条書きにしていくんですよ。そうやって書いていると、だんだん思考が凝縮されていって、電話しないといけなかったことを思い出したり、カレンダーに入れ忘れていた用事が出てきたりと、仕事が発生して[...]なんでも一つのツールに放り込んでいく作戦。
私も PC では Emacs、スマホでは「黄色いメモ」(後述)にどんどん脈絡なくメモしていっているなあ。
瀬下 書き上がった原稿がすでにあって、それをWordにコピペするだけ、という感じにしたいですよね。これ、すごくわかります。Word が DTP ソフトみたいなものになってる。
山内 あと、たぶんツイッターやアウトライナーを使いだしてから一段落が短くなりましたね。これもわかる。ブログ書くのも同様の効果ありかと。
せっかくなので、アウトライナーのうち、たびたび取り上げられている「workflowy」を使ってみました。MacBook と iPad mini で。
まあ悪くはないのですが、普段使いする感じではないかな。本とか長い論文とか書く機会あればお世話になるかも。

仕事もプライベートも基本的に、Apple の黄色いメモ[2013-01-16-1]と Emacs[2007-01-11-1] で事足りています。こういう長期間使うツールは、途中で消えたり終わったりすると嫌なので、結局定番のものに落ち着くんですよね。「黄色いメモ」は8年くらい、Emacs に至っては四半世紀以上(28年?)使い続けています。
文章を書くための正反対の二つの方法 (読書猿):
- 書くべきこと(NTW:need to write) を先に定めてから書く
- とにかく書けること(ATW:able to write) から書いていく
上述の時間の制約(〆切)の話についての読書猿さんの言葉。
次のことは認めなくてはならない。実のところ、自分に対する要求水準の上昇は、執筆に対する高い意識がもたらすのではなく、ただ〈完成させることを引き延ばす〉という病の一つの症状にすぎないのだ。
何を書こうかと考えて書くのではなく、書くことが自然とそこにあるときに書く。そこに何かあるなら、きちんと書こうとしなくていい。そこにあるものがポツポツと言葉になり始めたなら、それはメモ段階ではなく、もう本文であり、そこでメモと本文を区別しなくていい。 (千葉)ATW ですね。
複雑な事象はよくも悪くもある観点から線形化され、物語化されてしまうのだが、有象無象の記録を日誌へ、中間的テクストへと変換する段階で、自分が注目してしまっている出来事とその解釈可能性に気づき、書くべきことが、章立てさえもが見えてくる。 (山内)書き続けているということが大切という話(と解釈しました)。
データがなければ分析もできない、みたいな。
千葉 リズム感もあるし「最初に出てきたものに真実がある」という一種の信仰ですね。最初から出てきたものは、後から分析して出てきたものよりも情報がたくさん含まれていることが多いと思ってるんです。それを分解して再構成すると情報量が減ってしまう。減ってもいいようにわざと冗長に書いたりもします。
推敲漏れでおかしくなっちゃったりすることもあるけど。
瀬下 ぼくは文章執筆に関する手法や習慣は絶えず再構築されるものだと思っています。いまは効果を発揮していても、状況が変わったら効果はなくなるかもしれないし、そうなれば別の方法を考えるしかない。結局これですよね。常により良いものを探し続ける。その上で今のがベストならばそれで行く。でも、新しいものも少し取り入れる。そんな感じ。
読書メモ的なものは以上です。
私のライティングの哲学の一つとして「オチ(シメ)にこだわらない」というのがあります。ということで、当ブログ記事はこれでおしまい。
- 千葉雅也, 山内朋樹, 読書猿, 瀬下翔太 / ライティングの哲学 書けない悩みのための執筆論 (星海社 e-SHINSHO)

書くのが苦しい4人と一緒に「書けない」悩みを哲学しよう!
「書き出しが決まらない」「キーボードに向き合う気力さえ湧いてこない」「何を書いてもダメな文章な気がする」……何かを書きたいと思いつめるがゆえの深刻な悩みが、あなたにもあるのではないでしょうか?
本書は「書く」ことを一生の仕事としながらも、しかしあなたと同じく「書けない」悩みを抱えた4人が、新たな執筆術を模索する軌跡を記録しています。
どうすれば楽に書けるか、どうしたら最後まで書き終えられるか、具体的な執筆方法から書くことの本質までを縦横無尽に探求し、時に励まし合い、4人は「書けない病」を克服する手がかりを見つけ出します。
さあ、あなたも書けない苦しみを4人と哲学し、分かち合い、新たなライティングの地平へと一緒に駆け出していきましょう!!
目次:
- はじめに 山内朋樹
- 座談会その1
- 挫折と苦しみの執筆論
- Section.1 「書くこと」はなぜ難しいのか?
- Section.2 制約と諦めのススメ
- Section.3 「考えること」と「書くこと」
- 執筆実践
- 依頼:「座談会を経てからの書き方の変化」を8000文字前後で執筆してください。
- 断念の文章術 読書猿
- 散文を書く 千葉雅也
- 書くことはその中間にある 山内朋樹
- できない執筆、まとめる原稿ーー汚いメモに囲まれて 瀬下翔太
- 座談会その2
- 快方と解放への執筆論
- Section.1 どこまで「断念」できたか?
- Section.2 「執筆」の我執から逃れ自由に「書く」
- あとがき 千葉雅也
